オウンドメディアを始めたけど、思うように成果が出ない…そんなふうに感じていませんか?やる意味があるのか、このまま続けていいのか迷ってしまいますよね。
この記事では、オウンドメディアが意味がないと言われる理由やよくある失敗パターン、どうすれば成功できるのかをわかりやすくまとめています。
内容は次の通りです。
・意味がないと言われる8つの失敗例
・失敗の本当の原因
・成果につなげるKPIや評価指標の考え方
・費用対効果のチェックポイント
・具体的な成功事例と運用のコツ
オウンドメディア運用で悩んでいる方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
目次

オウンドメディアは多くの企業が導入し、ブランディングやリード獲得、長期的な集客基盤の構築を目指すマーケティング施策の一つです。しかし近年「オウンドメディアは意味がない」と感じる企業や担当者が増えています。その背景には、短期間での成果が見込めない、投資対効果の測定が難しい、リソース不足など複数の課題が存在します。本章では、オウンドメディアが意味ないとされる理由を整理し、正しい理解と対策の糸口を提示します。
オウンドメディアとは、企業や組織が自ら所有・運営するウェブサイト、ブログ、メールマガジン、SNSアカウントなどを指します。これらは自社でコントロールできる情報発信の場であり、広告やアーンドメディア(第三者による紹介)とは異なり、自由度の高いブランディングや見込み顧客の獲得、既存顧客との関係強化など様々な目的に活用されます。
近年はコンテンツマーケティングの中核として、SEO対策を意識した記事やノウハウ、事例紹介、ホワイトペーパー、動画コンテンツなど多彩な情報発信が行われています。オウンドメディアは顧客の購買行動の入り口となるケースが多く、検索エンジンからの流入やSNSでの拡散によって新規リードの獲得やブランド価値向上に寄与します。ただし、成果創出には戦略・ターゲット・運用体制・KPI設計など多面的な視点が不可欠です。
オウンドメディアの意味がないと判断される主なきっかけは、期待した成果が得られない場合です。
具体的には、以下のようなタイミングで意味がないと感じられがちです。
これらの状況は、戦略や体制、マーケティングフロー、社内理解など複合的な要素が絡み合うため、単純な「記事が少ない」「SEOが弱い」だけではなく、運営全体の設計に問題があるケースが多いです。
オウンドメディア運用が意味がないと言われてしまう背景には、共通する失敗パターンが存在します。主なパターンを8つ挙げ、それぞれの問題点と改善ポイントを解説します。
明確な戦略やコンセプトを持たずにオウンドメディアを始めてしまうと、ターゲットやゴールが曖昧になり、記事更新が目的化したり、方向性のぶれたコンテンツが量産されてしまいます。最終的に「何のために運用しているのかわからない」意味がないと感じてしまう原因になります。
戦略設計では、なぜ自社がオウンドメディアをやるのか(ブランド認知なのか、リード獲得なのか、採用強化なのか)を明確にし、KGIから逆算したKPIと運用方針を決めることが重要です。戦略不在は、社内の合意形成の欠如や、担当者のモチベーション低下、投資対効果の不明瞭化にも直結します。
オウンドメディアのターゲットユーザー像(ペルソナ)が曖昧だと、誰のためのコンテンツなのかが不明確になります。例えば、自社商品やサービスの購買者とは異なる層に向けて記事を発信してしまい、アクセスは集まるがCVに繋がらない、という事態が起こります。
ターゲットを明確に設定し、そのペルソナの課題やニーズ、購買行動や情報収集経路を分析した上でコンテンツ設計を行うことが、成果のある意味あるオウンドメディア運用の第一歩です。
SEO対策やユーザー満足度向上の観点から、質の高いコンテンツと十分な量の蓄積は不可欠です。
これらはすべて、意味がないと判断される要因です。GoogleもE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視し、質・量・独自性がなければ上位表示は困難。
また、継続的な記事追加・リライトを通じてコンテンツを資産化する視点も重要です。
オウンドメディア運用の目的や期待する成果(KGI/KPI)が曖昧な場合、何を持って成功とするかの判断ができません。
例えば、PVやUUだけを追ってもコンバージョンに繋がらなければビジネス効果は限定的ですし、ブランド認知や採用など定性的な目標の評価軸が設定されていないと、成果の可視化ができず意味がないとなりがちです。
KPI設計は運用体制やコンテンツ制作の指針となるため、運営開始前にしっかり設計しましょう。
オウンドメディアはSEOやブランド構築を中心とした「中長期施策」です。数ヶ月で結果が出る施策ではありません。
立ち上げ初期はGoogleからの評価が定着せず、アクセスやリードも限定的になりがちです。長期的な運用と改善サイクルを前提にしないと意味がないと早期に見切りをつけてしまうリスクがあります。
期待値を適切に設定し、短期・中期・長期それぞれのKPIを設計することが肝要です。
検索エンジン最適化(SEO)やSNS活用、メールマーケティングなど、集客チャネルの設計が不十分だと、せっかくのコンテンツもユーザーに届きません。
SEOキーワード選定や内部リンク設計、競合調査、SNS・広告・外部施策などを体系的に設計しないと、集客が頭打ちとなり意味がない状況に陥ります。
集客施策はコンテンツの質・量と同時に強化が必要です。
オウンドメディア運用には、戦略設計・ディレクション・編集・執筆・SEO・分析・改善など多様なスキルと継続的なリソース投入が不可欠です。
これらがボトルネックとなり、PDCAサイクルが回らずに意味がないと判断されてしまいます。外部パートナーや制作支援会社の活用も検討しましょう。
オウンドメディアの効果を最大化するには、定期的な分析と改善(PDCA)が不可欠です。Googleアナリティクスやサーチコンソールなどでアクセス解析し、KPI未達時には記事リライトや新規施策投入を行う必要があります。
分析や改善が形骸化、あるいは実施されていない場合、戦略の修正やコンテンツの最適化が進まず、資産としての価値が積み上がりません。結果として意味がないとされてしまいます。
オウンドメディアは広告のような短期的な成果が見えづらく、定量的なROIの算出や社内外への説明が難しい施策です。
こうした理由から、オウンドメディアは意味がないと感じられやすい側面があります。
しかし、正しい戦略設計とKPI管理、運用体制の確立、継続的な改善を行えば、ブランド資産やリード獲得、SEOでの流入増加など大きな効果を生み出すことが可能です。
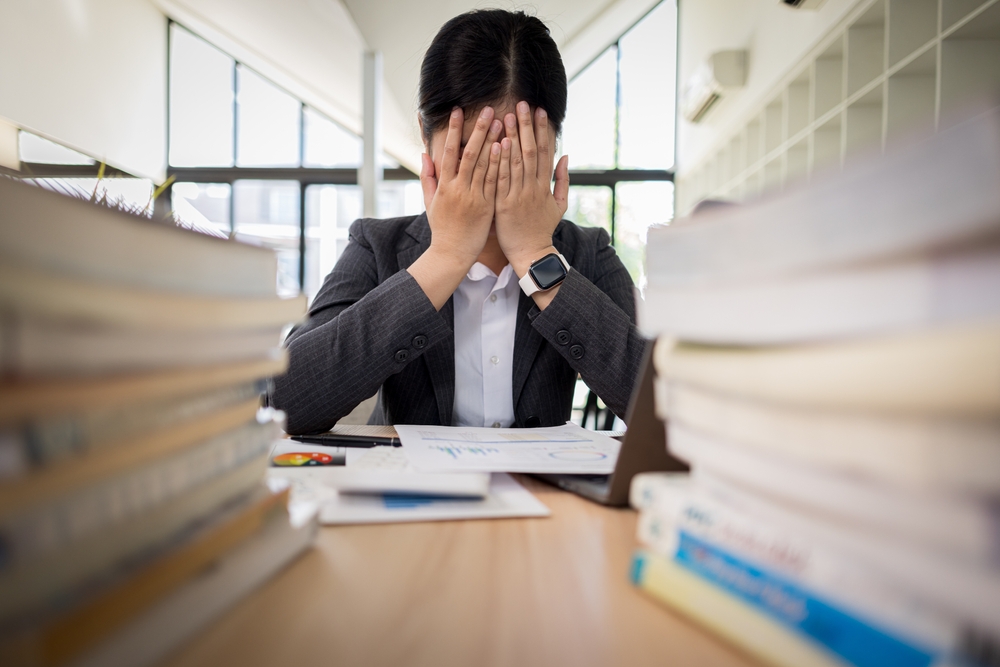
オウンドメディアの失敗は「記事が読まれない」「アクセスが伸びない」といった表面的な現象だけでなく、運用の根本にある構造的な問題が要因となることが多いです。ここでは意味がない状態に陥る本質的な原因を、戦略・体制・評価軸の観点から解説します。
オウンドメディア運用で最も多い失敗は、事業目的とメディアのゴールが一致していないことです。例えば、リード獲得を目的としながらもブランド認知向上のためのコンテンツばかり発信したり、KGIが不明確なままPVやUU(ウェブサイトに訪れた人数)など定量指標だけを追いかけてしまうと、ビジネス成果に直結せず意味がないと感じやすくなります。
ゴール設計の段階で、事業全体のKGI(例:売上・リード数・採用数など)とオウンドメディアの役割・KPI(例:資料請求数・問い合わせ数など)を明確にリンクさせることが重要です。目的と手段のミスマッチを防ぐことで、成果の可視化と納得感のある運用が実現します。
オウンドメディアのコンテンツ戦略において、ターゲットユーザー=ペルソナの設定が不十分だと、訴求力のあるコンテンツを作成できません。
ペルソナの属性(年齢・性別・職業・業種・役職・課題・購買行動・情報収集チャネルなど)を具体的に描ききらないまま運用を始めると、「誰に向けた記事か分からない」「実際の顧客に刺さらない」などの問題が発生します。
ペルソナ設計は、SEOキーワード選定やコンテンツ企画、CV導線設計にも直結するため、運用初期に徹底的に深掘りしておきましょう。
「オウンドメディア=記事を量産すれば成果が出る」「SEOキーワードを多用すれば上位表示できる」といった誤解が散見されます。
現在のSEOでは、単なる記事数やキーワード出現率ではなく、ユーザーの検索意図に基づいた網羅性・独自性・専門性・信頼性が重視されます。また、「自社の強み」「独自のナレッジ」「一次情報や実績」など競合との差別化がなければ、検索順位もCVも伸びません。
コンテンツマーケティングの本質は「価値ある情報をターゲットに届け、行動を喚起すること」です。誤解を排し、戦略的に運用しましょう。
オウンドメディアの失敗例で多いのが、社内体制や運用フローの不備です。
このような状況では、PDCAサイクルが回らず、記事の質や運用スピードが低下します。
運用体制の整備・役割定義・進捗管理ツールの活用など、仕組み化が必須です。
オウンドメディアのKPIや評価指標が「PVや記事本数だけ」「CV数だけ」といった偏った設定だと、本質的な成果を見逃しやすくなります。
例えば、コンバージョンまでの間接効果やブランド価値の向上、採用母集団形成への貢献など、定性的・間接的な成果も評価対象に含める必要があります。
定量指標(PV・UU・CVなど)と定性指標(ユーザーの声・SNS反響・ブランド認知)をバランス良く設定し、定期的に見直しましょう。
オウンドメディアを意味がない施策にしないためには、運用目的に応じたKPIと評価指標(KGI・KPI・定量・定性)を明確にし、PDCAサイクルを継続的に回すことが不可欠です。ここでは、成果を出すためのKPI設計のポイントと具体例、モニタリング・改善手法まで網羅的に解説します。
KPI(主要業績評価指標)は、事業ゴール(KGI)から逆算し、オウンドメディアの運用目的に直結する指標を選定することが重要です。
例えば、リード獲得をKGIとする場合は「問い合わせ数」「資料請求数」「商談化率」などがKPIとなります。ブランド認知が目的なら「指名検索数」「SNSシェア数」「アンケートによる認知度」などが該当します。
KPI設計のポイントは、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:事業関連性、Time-bound:期限)に沿って、関係者と合意を取ること。
KPIを定量的に設定することで、運用の進捗や課題を客観的に把握できます。
オウンドメディアでよく使われるKPIは以下の通りです。目的によって組み合わせや重み付けを調整しましょう。
| 目的 | KPI例 |
| 集客 | PV(ページビュー)、UU(ユニークユーザー)、新規訪問率、検索順位 |
| リード獲得 | CV(コンバージョン数)、問い合わせ数、資料請求数、メルマガ登録数 |
| ブランド価値向上 | 指名検索数、SNSシェア数、ブランド名での言及数 |
| ユーザーエンゲージメント | 平均滞在時間、回遊率、コメント数、シェア・いいね数 |
KPIを複数設定し、フェーズごと(初期はPV/UU、中期はCV/リード数、後期はLTVや商談化率など)に重心を移すのも有効です。
オウンドメディアは短期的な施策ではなく、中長期的な成果を目指す資産型のマーケティングです。SEOやブランド認知の定着には半年~数年の継続投資が必要なため、短期間でKPI未達でも焦らず、中長期で評価する体制が求められます。
定期的なマイルストン設定(3ヶ月・6ヶ月・1年など)や、KPIの進捗を振り返るレビュー会議、必要に応じた戦略修正を組み込むことで、長期的な視点で運用の最適化が可能です。
また、KPI未達時も「何がボトルネックか」「コンテンツの質・量・SEO・導線・体制のどこに課題があるか」を分析することで、次のアクションに繋げましょう。
オウンドメディアの評価は、定量指標(数値で測れるKPI)と定性指標(ユーザーの声やブランド認知など主観的な成果)をバランス良く組み合わせることが重要です。
KPIの進捗はGoogleアナリティクスやサーチコンソールなどで定期モニタリングし、定性評価はユーザーアンケートやヒアリング、SNS分析で補完しましょう。
これにより、数値化しにくいブランド価値やファン化、リードの質向上なども評価でき、オウンドメディアの「本当の意味」を可視化できます。
成果を最大化し、意味がない施策とされないためには、KPIのモニタリングと改善(PDCAサイクル)が不可欠です。
例えば、PVや検索順位が伸び悩んでいる場合は、キーワード選定や記事リライト、内部リンク設計を見直す。CVが伸びていない場合は、CTA(行動喚起)や導線、記事内容の見直し、ターゲットの再定義を行う。
モニタリングにはGoogleアナリティクス、サーチコンソール、ヒートマップツール、SNS分析など多様なツールを活用し、定量・定性両面から評価しましょう。
改善サイクルを仕組み化することで、オウンドメディアは意味がないどころか、着実に成長と成果を積み上げる資産となります。

オウンドメディアの費用対効果を正しく判断することは、企業の持続的な成長やマーケティング戦略の最適化に不可欠です。多くの担当者が「オウンドメディアは意味ないのでは」と感じる背景には、投資額に見合うリターンが実感できない、または成果の可視化が難しいという課題が存在します。オウンドメディアは中長期で資産化し、ブランド認知やリード獲得など多様な効果をもたらしますが、その評価を感覚や短期成果だけで判断してしまうと、継続すべき価値を見誤るリスクがあります。本章では、オウンドメディアの費用対効果(ROI)を具体的にどう捉えるべきか、広告・SNSとの違い、継続投資と撤退基準、成果が現れるまでの期間の見極め方までを詳しく解説します。
オウンドメディアのROI(投資対効果)は、単に「どれだけアクセスが増えたか」「記事本数が増えたか」だけでなく、実際にビジネスにどれだけ価値を生み出しているかを測る指標です。
具体的には、オウンドメディアの運用にかかるコスト(人件費、制作費、外部委託費、システム運用費など)と、そこから得られる成果(リード獲得件数、資料請求、問い合わせ、受注件数、売上、ブランド認知度向上、採用エントリー数など)を数値化し、比較することが求められます。
例えば月間運用費が30万円、月間リード獲得数が50件、そのうち10件が商談化し2件が受注、受注単価が50万円なら、ROIはプラスになります。
重要なのは、単発のKPIだけでなく、中長期で見込めるリターンや間接的な効果(ブランド力・SEOによる資産化)も含めてROIを評価する視点です。
定性的な効果も合わせて可視化し、「オウンドメディアは意味ない」ではなく、「どうすれば意味ある投資にできるか」を検討しましょう。
オウンドメディアの費用対効果を考える上で、広告やSNSと比較した際のコスト構造や持続性・資産性の違いを理解しておくことは必須です。
| 施策 | 主なコスト | 成果の特徴 | 資産性 |
| 広告(リスティング・ディスプレイなど) | 広告出稿費・LP制作費・運用手数料 | 即時的な流入・CV獲得が可能だが、広告停止とともに成果も止まる | 低い |
| SNS(Twitter、Instagramなど) | 運用人件費・広告費・制作費 | 拡散力・話題化に強いが、アルゴリズムや流行の変化に左右されやすい | 中 |
| オウンドメディア | 初期立ち上げ費・記事制作費・運用人件費・SEO対策費 | 立ち上げ当初は成果が見えにくいが、検索エンジン経由での安定した集客・リード獲得が積み上がる | 高い |
オウンドメディアは、短期的なアクセス増加や即効性では広告やSNSに劣る場合もありますが、継続的に資産となるコンテンツを蓄積できるため、長期的な費用対効果は非常に高くなります。
意味がないと判断する前に、広告やSNSとの役割の違いを明確にし、組み合わせて運用することが、最適なマーケティング戦略に繋がります。
オウンドメディアの運用では「どこまで投資し続けるべきか」「成果が見込めない場合は撤退すべきか」という判断が必要になります。
重要なのは「適切な評価期間を設け、定量・定性両面から投資判断を下すこと」です。短期の未達だけで意味がないと切り捨てず、改善余地や市場動向を踏まえた分析が不可欠です。
オウンドメディアはSEOを中心とした施策であるため、成果が現れるまで半年~1年以上かかることが一般的です。
目安としては、
ただし、業界の競争環境、キーワード難易度、運用体制、SEO施策の精度によって成果が出るタイミングは異なります。
定期的にKPI進捗をチェックし、成果の兆しが見え始めるまでは冷静に投資を継続することが肝要です。意味がないと感じる前に、想定期間と成果の見極め方を事前に設計しましょう。
オウンドメディアを意味がないものにしないためには、実際に成果を上げている企業の事例分析と、運用のコツを体系的に学び、実践することが不可欠です。本章では、成功している企業に共通する特徴、BtoB・BtoCそれぞれの成功パターン、そして日々の運用で押さえるべきポイントを詳細に解説します。
オウンドメディアで高い成果を上げている企業には、以下の共通点があります。
こうした仕組みを作れない場合、意味がないと感じやすくなります。成功企業の特徴を参考に、自社の運用体制や評価軸を見直しましょう。
BtoB企業におけるオウンドメディアの成功事例としては、専門性の高いコンテンツ(業界ノウハウ、比較・検証記事、導入事例など)を継続的に発信したことで、検索上位表示・リード獲得・商談化率向上・営業効率化に大きく貢献したケースが多く見られます。
例:ITサービス企業が「業界動向」「最新技術解説」「成功事例」などのSEO最適化コンテンツを発信→月間リード数が100件超、商談化率も大幅アップ。
BtoB領域は検討期間が長く、意思決定に複数人が関わるため、信頼性・専門性・網羅性が成果のカギとなります。オウンドメディアの意味を最大限に引き出すためには、業界特化の情報発信、一次情報や独自レポートの活用が不可欠です。
BtoC(消費者向け)分野では、ユーザーの悩みや疑問に寄り添った記事や、購入体験談、ランキング・比較記事などをSEO観点で最適化することで、集客・リピート率向上・SNS拡散などに成果を上げている事例が多くあります。
例:美容系サービスが「お悩み解決」「体験レビュー」「商品比較」などユーザー目線の記事を量産し、月間PVが10万超、検索経由のリピート購入や問い合わせが大幅増加。
BtoC領域では検索ボリュームが大きい分、競合も多いですが、「ユーザーが本当に知りたい情報」を徹底的に網羅することがオウンドメディアの意味を最大化します。
オウンドメディアで意味がないと言われないためには、日々の運用で意識すべきポイントがあります。以下の3つを徹底することで、成果を最大化できます。
オウンドメディアのコンテンツは、企業目線ではなく「ユーザーが本当に知りたいこと」「ユーザーの課題・悩み・検索意図」を徹底的に深掘りし、わかりやすく解決策を提示することが重要です。
こうしたユーザー視点の記事は検索評価も高まりやすく、SEOでも強いオウンドメディアとなります。意味がないと思われない最大のポイントです。
Googleアナリティクス・サーチコンソール・ヒートマップ・SNS分析などのデータを活用し、
を定期的に可視化して改善策を実施します。
データに基づいたリライトや構成変更、キーワード最適化、CTAの見直しなどを継続すれば、オウンドメディアの意味は着実に高まります。「感覚」や「思い込み」だけの運用は意味ない状態を招くため、必ずデータドリブンな改善を心がけましょう。
オウンドメディアの運用には、企画・編集・執筆・SEO・デザイン・分析など幅広い役割が求められます。
など、多様なリソースを組み合わせることで、運用効率とコンテンツの質を両立できます。リソース不足や属人的な運用でPDCAが止まると意味がない施策になりがちです。
必要に応じて外部リソースやツールも導入し、持続的な運用体制を構築しましょう。
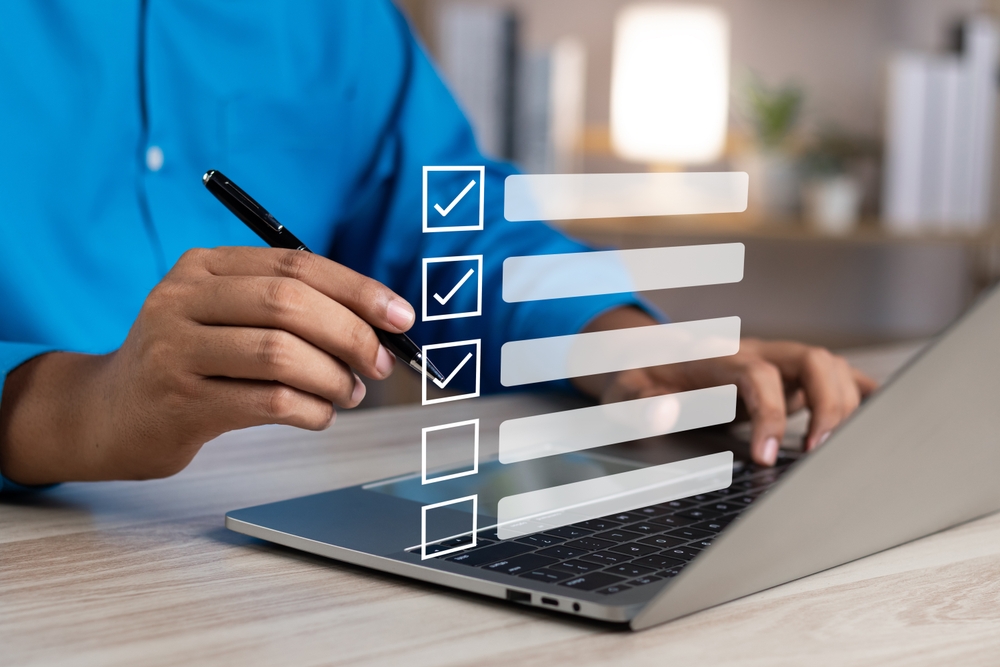
オウンドメディアを意味がない投資にしないためには、運用開始前から運用中、成果が出ない場合の見直しまで、段階ごとのチェックリストを活用することが極めて有効です。本章では、失敗を未然に防ぐための具体的な確認項目・見直しポイントを整理しました。
オウンドメディア立ち上げ前の事前準備は、成功・失敗を大きく分ける最重要ポイントです。以下にチェックリストを示します。
これらを怠ると「何となく始めて意味ないまま終わる」リスクが高まります。必ず全ての項目をチェックして立ち上げましょう。
オウンドメディア運用中は「やりっぱなし」にならないよう、定期的な見直しが欠かせません。特に重要な見直しポイントは以下です。
これらを四半期・半年ごとに見直すことで、成果を最大化し意味がないとならないオウンドメディア運用が実現できます。
オウンドメディアのKPIが未達、または意味がないと感じる場合は、以下の手順で見直しと改善を徹底しましょう。
このPDCAサイクルを高速に回すことで、オウンドメディアの意味がない状態を脱却し、再成長させることが可能です。
失敗を恐れず、改善サイクルを回し続けることが成功への最短ルートです。
オウンドメディアの運用において意味がないと感じる主な要因は、費用対効果の評価方法が曖昧、短期的な成果のみで判断してしまう、戦略・体制・評価軸が不十分、改善サイクルが回っていないなどに集約されます。
成功するためには、運用目的とゴールを明確にし、中長期のKPIと評価指標を設計、広告・SNSとの役割の違いを理解した上で費用対効果を冷静に判断することが不可欠です。
また、成功企業の事例・コツを参考に、ユーザー視点のコンテンツ、データ分析に基づく改善、社内外リソースの柔軟な活用を意識しましょう。
定期的なチェックリスト活用とPDCAサイクルの徹底によって、意味がない状態を未然に防ぎ、オウンドメディアの本当の価値・資産性を最大限に引き出せます。
中長期視点を持ち、継続的な運用改善を実践し続けることこそが、オウンドメディアで成果を出し続ける唯一の道です。
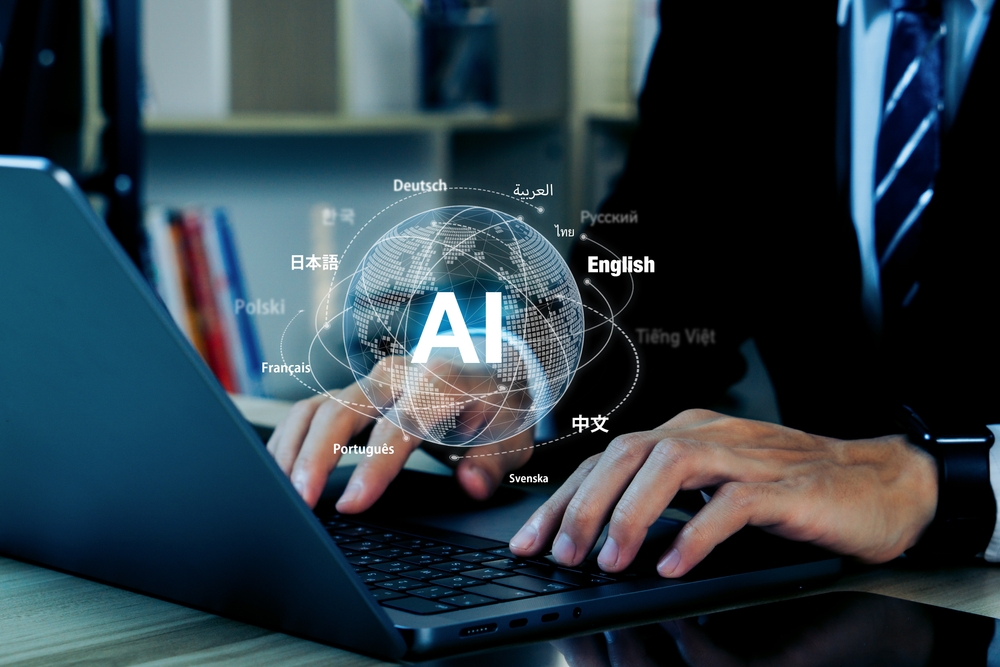
オウンドメディアを運用をしたいけど「方法がわからない」「リソースが足りない」という際はProteaにご相談ください。
ご希望や目的などをに併せ、各社にあった提案をさせていただきます。
お問合せはこちら
また、AI記事サービスの「AIフォースSEO」も提供しております。
AIフォースSEOは1記事5,000円から作成可能な記事生成サービスです。
キーワード選定がプラスされたプランもご用意しております。
SEO対策を実施したいけど、自社にノウハウがない、リソースが足りないなどでお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
AIフォースSEOのお問合せはこちら
この記事を書いた専門家(アドバイザー)
著者情報 プロテア
WEBマーケティングの領域で様々な手法を使い、お客さまの課題を解決する会社です。