「自社のようなBtoB企業でも本当にSEO対策は必要なのか?」「限られた人手や時間で効率よく進める方法は?」などと悩んでいませんか。
特にBtoBの場合、購買プロセスが長期化しやすく、検討段階での情報収集も複数の担当者が関わるなど、BtoCとは異なる側面があります。そこで本記事では、BtoB企業こそSEO対策に取り組むべき理由や、実際の成功事例、具体的な進め方や運用のコツ、そして他施策との違いやリスクなどを詳しく解説します。
BtoB企業のマーケティング担当者として、どのようにSEOを組み込み、成果につなげればよいのかを網羅的にまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
Table of Contents

BtoB企業がSEO対策を行う意義は多岐にわたります。購買担当者が商品やサービスを探す際、多くの場合はインターネットで情報収集を行うのが一般的です。ここで自社サイトが検索結果の上位に表示されていなければ、そもそも候補として検討されない可能性が高くなります。
さらに、BtoBの商材は専門性が高く価格も大きいことが多いため、検討期間が長引き、複数の意思決定者や関係者が関与します。こうした特徴から、長期的・継続的な情報発信と接点形成が必要となり、SEOはその基盤を築くうえで不可欠な手段です。また、SEO対策を継続することで、広告費の削減やターゲット企業からの信頼度向上、商談化率アップなど、幅広いメリットが期待できます。
BtoBビジネスでSEOが重視される背景としては、近年の購買行動が「担当者自身による事前調査」へと大きくシフトしている点が挙げられます。ある調査では、BtoB企業の購買プロセスの57%が、営業担当と接触する前に完了しているというデータもあります。
専門的で高額な商材ほど、複数の比較検討が行われ、あらゆる情報が精査されるため、Web上の情報が少ない企業は検討対象から外されがちです。SEOにより関連キーワードで検索上位を獲得し、見込み顧客に信頼性の高い情報を提供できる企業こそが、商談の入り口を押さえることができます。
また、BtoBの取引ではニッチなキーワードでも成約に直結しやすいケースが多いため、ビッグワードだけではなく、専門用語や業界特有の課題に即したキーワード対策によって、高品質なリード獲得が見込めます。
BtoB企業がSEO対策に取り組むことで得られる代表的なメリットは下記の通りです。
このように、SEO対策はBtoB企業にとって単なる流入拡大策ではなく、事業成長や競争力強化を支える重要な柱となります。専門性の高い商材でも、見込み客が検索エンジンを通じて情報収集を行う以上、SEOは外せない施策と言えるでしょう。
BtoB企業のマーケティングには、広告、展示会、テレアポ、ウェビナーなど多彩な手法があります。これらと比べたとき、SEOの特徴は「長期的な資産化」と「ユーザーの検索意図に寄り添った集客」が挙げられます。
広告や展示会は短期間での効果が期待できる反面、費用をかけ続けなければ成果が途切れやすいものです。一方、SEOは時間をかけて蓄積したコンテンツや被リンクなどの評価が長期にわたり機能するため、費用対効果の高い集客チャネルとなります。
また、検索エンジンを使って情報を得ようとするユーザーは「解決したい課題」や「導入したいサービス」のニーズが明確である場合が多いことも魅力です。購買意欲が高い段階で接点を持つことができるため、商談獲得や成約率アップにも大きく貢献します。
もしBtoB企業がSEO対策を行わない場合、潜在顧客との接点を他社に奪われるだけでなく、ブランド力や競合優位性にも大きな差がついてしまいます。特に近年はデジタルでの情報収集が当たり前になっているため、検索結果で見つからない企業は「存在していない」のと同義と捉えられてしまう恐れもあります。
その結果、広告費を増やさないとリードを獲得できなくなる、あるいは展示会やテレマーケティングなど従来型の施策に依存せざるを得ず、コストばかりかかって効率が下がるリスクも考えられます。中長期的に成長をめざすのであれば、SEOを無視することは大きな機会損失となるでしょう。
検索エンジン経由の流入は、課題意識が高い顧客との出会いの場でもあります。SEOをしないことで、その接点自体が生まれず、リードをほぼ自動的に失うことになってしまいます。BtoBでは商材単価が高いため、1件のリードの価値も大きいケースが多いです。こうした有望顧客を逃すのは大きな痛手と言えます。
競合他社がすでにSEOに注力している場合、自社だけが未対応だと検索結果で埋もれ、ブランド認知や信頼度を下げる要因となります。情報収集段階の見込み顧客にとって、検索上位に表示されるコンテンツは「まず参照すべき情報源」として認知されやすいため、徐々に商談数や受注率にも大きく差がついてしまうでしょう。

実際にBtoB企業がSEOで成功している事例を見ると、専門性やニッチなキーワードへのアプローチが成果につながっているケースが多いです。本章では、問い合わせ数の増加事例や、ITサービス・製造業の具体的なSEO活用方法をご紹介します。成功企業の取り組みを参考にすることで、自社の戦略をブラッシュアップできるでしょう。
BtoB企業がSEO対策を強化した結果、問い合わせやリード数が大幅に増えたという話は珍しくありません。ここでは、キーワード選定や専門性の高い記事制作を徹底し、実際に成果を上げた事例を見ていきます。
あるITサービス企業では、「業務効率化 SaaS」「DX推進 中小企業」といったキーワードで上位表示を獲得し、問い合わせが月ベースで3倍に増加しました。
成功要因は、単なる製品紹介ページだけでなく、導入事例や具体的な課題解決方法を丁寧に解説した専門性の高いコンテンツを充実させたことです。また、ホワイトペーパーのダウンロードや無料相談への導線を分かりやすく配置することで、SEO経由のリード獲得率を大きく向上させました。
製造業のBtoB企業でも、部品調達やOEM、試作開発などニッチな領域でSEO対策を行い、月間リード数を2倍以上に伸ばした事例があります。
具体的には、製品スペックや品質管理体制など専門的な情報を多角的に発信し、業界特有のキーワードを網羅することで検索上位を獲得しました。高付加価値なリードが増えただけでなく、商談化率も向上している点が特徴です。
成果の出ているBtoB向けSEOコンテンツには、専門性とユーザー目線に配慮した構成が共通点として見られます。特に「現場で使える具体的な情報」や「一次データ・信頼できる統計」など、他では得られない付加価値を提供している点がポイントです。
専門性の高いコンテンツとは、業界固有の課題や技術的背景、法規制、導入プロセスなどを踏まえた解説記事を指します。単なる知識の羅列ではなく、自社の現場ノウハウや失敗事例・成功事例を交えつつ、読み手に「ここでしか得られない情報がある」と感じさせることが重要です。
また、適切なデータソースや専門家のコメントなどを引用し、信頼性・客観性を高める工夫も欠かせません。
BtoB企業の担当者は、業務効率化やコスト削減といった具体的な課題に直面しています。そこで、記事では「現場の悩みをどう解決するか」という視点を明確にし、手順やチェックリストなど「すぐに試せる方法」を提示することで高い評価を得られます。
ユーザーの課題を深堀りし、「共感→解決策の提示→事例紹介」という流れを組み込むと、SEOの評価向上だけでなく、信頼関係を築きやすくなるメリットがあります。
BtoB企業がSEOで成果を上げている事例に共通するポイントは以下の4つです。
これらを踏まえて施策を展開することで、BtoB企業は長期的なリード獲得を実現しやすくなります。特にニッチキーワードを軸に、専門的なコンテンツを継続発信する取り組みは非常に効果的です。

BtoB企業がSEOで成果を出すには、戦略立案から効果検証までを一貫して行うことが大切です。ここでは具体的なプロセスとして「戦略立案→キーワード選定→ペルソナ設計→コンテンツ制作→内部・外部施策→効果分析・改善」の流れを解説します。段階を踏んで取り組むことで、無駄を省きながら効果を最大化できます。
まずは、自社がSEOに取り組む目的を明確にすることが重要です。例えば「毎月の新規リードを増やす」「問い合わせ数を1年で2倍にする」など、具体的なKPIを設定します。
次に、ターゲットとなる業界や役職者の課題・ニーズを掘り下げ、自社の強みと競合の状況を分析しましょう。ここで差別化の軸を見出し、その軸を活かせるキーワード戦略やコンテンツ方針を立てることで、より効果的なSEO施策を展開できます。
キーワード選定はSEO成功の要です。BtoBの場合はビッグキーワードだけでなく、ニッチな専門用語や特定の課題・ソリューションを想起させるワードを含めてリサーチします。
ツールとしてはGoogleキーワードプランナーやラッコキーワード、ahrefsなどが有名ですが、実際の顧客や営業担当から「どんな言葉で検索するか」をヒアリングすることも効果的です。
さらに、購入検討フェーズごとにキーワードを整理し、潜在層向け・比較検討層向け・導入直前層向けなど、複数ステージを意識したキーワードマップを作成すると施策が進めやすくなります。
BtoBの購買決定には複数のステークホルダーが関わるため、担当者(現場レベル)と決裁者(経営層)など、複数のペルソナを想定することが大切です。
例えば、「従業員100名規模の製造業で情報システム導入を検討している課長」という具体的な設定を行い、ニーズ・悩み・検索時のキーワードなどを洗い出します。
ペルソナを細かく設計するほど、狙うべきキーワードや制作すべきコンテンツが明確になり、結果的にCV(問い合わせ・資料請求など)率を高めることにつながります。
実際の制作フェーズでは、テーマ選定と構成案作成、原稿執筆、レビュー・校正、公開・改善という流れで進めます。BtoBの場合、他社事例や業界トレンド、法規制など専門的な情報をカバーする必要があり、記事1本あたりのボリュームが大きくなる傾向にあります。
そのため、事前の構成作りが非常に重要です。あらかじめ見出し(H2、H3、H4)を設計し、情報の重複や漏れを防ぐことで、読みやすく質の高いSEOコンテンツを効率的に作ることができます。
テーマ選定では、先ほど整理したキーワードリストとペルソナ設定をもとに、どのような記事を優先的に作成すべきかを決めます。例えば、「BtoB向けクラウドサービスの導入プロセス」「部品調達コスト削減の具体的手順」など、検索意図がはっきりしたテーマが狙い目です。
構成案では、見出しの流れを意識して論理的に情報を並べ、読者が順序立てて理解しやすいよう工夫します。また、競合サイトをリサーチし不足している情報を補い、オリジナリティを出すことも大切です。
BtoB向けの記事では、専門用語の解説、業界動向の提示、導入メリットの具体的な数値化など、「専門性」と「実務視点」が重要になります。
加えて、導入事例や活用シーン、失敗事例など具体的なケースを示すと、読者の共感を得やすくなります。データや引用元は明示し、信頼性を高めることも大切です。
記事の最後には、資料請求や問い合わせへのリンクをわかりやすく配置し、リード獲得につなげる導線を明確にしておきましょう。
高品質なコンテンツを制作したら、次は内部SEOと外部SEOの両面でWebサイトを最適化します。内部SEOではサイト構造や内部リンクを整え、検索エンジンとユーザー双方にとって使いやすい設計を心がけます。
外部SEOでは、業界団体や提携先、専門メディアから自然な形での被リンクを獲得することが重要です。BtoBでは特に、権威性の高いサイトからのリンクが大きな評価を得やすいため、関連イベントや共同リリースなども活用すると効果的です。
サイト全体をピラミッド型の論理構造にし、カテゴリやタグの階層を明確にすることで、検索エンジンがページの関連性を理解しやすくなります。
また、パンくずリストや内部リンクの設計を整え、ユーザーが探している情報にすぐアクセスできる状態を作りましょう。ページの読み込み速度向上やモバイル対応などの技術的最適化も、離脱率の低減や検索順位の維持に効果的です。
外部からの被リンクは、検索エンジンに「このサイトは信頼に値する」というシグナルを与える重要な要素です。BtoBの場合、業界メディア、学会・協会、取引先など専門性の高いサイトからリンクを得られれば、評価が高まりやすくなります。
そのためには、自社サイトに「リンクしたい」「引用したい」と思わせる独自データや事例、オリジナルの調査結果を蓄積しておくことが有効です。無理なリンク獲得はペナルティを招く可能性があるため、自然な形でのリンクを心がけましょう。
SEOは公開して終わりではなく、運用しながら改善を続けることが重要です。定期的にアクセス解析やキーワード順位をチェックし、成果が出ていないページをリライトしたり、新たなキーワードを開拓するなど、PDCAを回すことで効果が高まります。
BtoBのSEOでは「自然検索からの流入数」「問い合わせ件数」「資料請求数」「キーワード順位」「ページ滞在時間」などをKPIとして設定します。
特にリード獲得に直結するコンバージョン指標を追うことで、SEO施策がどれだけ事業成果に貢献しているかを可視化できます。予め目標値を明確にしておき、月次や四半期ごとに達成度を確認しましょう。
SEO施策では、Plan(計画)→Do(実行)→Check(分析)→Action(改善)のプロセスを回し続けることが肝心です。
例えば、新しいキーワードで記事を作る(Do)→アクセス解析で確認(Check)→結果を踏まえてタイトルや本文を修正(Action)といったサイクルを繰り返し、高い成果を目指します。分析ツールや定例ミーティングを活用し、常に施策の打ち手をアップデートしていきましょう。

BtoB企業がSEOで継続的に成果を出すには、少人数体制ならではの進め方や、広告・SNSなど他チャネルとの使い分け、そしてよくある失敗例を回避するノウハウが欠かせません。ここでは、具体的な運用のコツと注意点を解説します。
中小企業や新規事業部などでは、SEOにフルタイムで割ける人員がいないこともしばしばです。こうした場合でも、基本的な進め方と役割分担を明確にし、外部リソースも上手に活用すれば、十分に成果を上げられます。
SEO戦略の設計やキーワードリサーチは社内のマーケティング担当が行い、専門性の高い記事執筆はフリーランスライターや外部の編集者に委託するなど、業務を細分化してそれぞれの強みを活かす方法が効果的です。
定期的に進捗を確認し、チャットツールやタスク管理ツールで情報を共有するなど、コミュニケーションの取りやすい体制を整えておくことが重要です。
社内リソースが限られる場合は、SEOコンサルティング会社や実績のあるWebライターとの提携が有効です。
専門知識を求められるBtoB向け記事でも、基本構成を社内が提示し、詳細の執筆を外部に依頼するなど、適切に役割を分担することでコンテンツの質と更新頻度を両立できます。ただし、最終的な内容チェックや独自の事例追加などは社内で行い、オリジナリティを保つようにしましょう。
SEOは中長期的な集客に強みがありますが、短期施策の広告や認知拡大に強いSNSと組み合わせることで、より幅広いリード獲得が期待できます。
例えば、新製品の発表時は広告で一気に露出を高めつつ、長期的にはSEOで安定した問い合わせを生む仕組みを整えるといった使い分けが効果的です。
広告は即効性が高い反面、費用がかかり続けるため長期的な運用にはコスト負担があります。一方で、SEOは成果が出るまでに時間はかかるものの、上位表示を獲得すれば安定的なリードが見込めます。
SNSは情報拡散やコミュニケーションに強く、ブランドの認知やファン育成に寄与する施策です。目的やターゲット、予算に応じて各施策を組み合わせることで、それぞれの弱点を補完し、成果を最大化できます。
BtoBの商材は導入までに時間がかかるため、問い合わせを受けた後のフォロー体制も重要です。
ホワイトペーパーやセミナー、ウェビナーなどを用いて見込み顧客の興味を育成し、購入意欲を高める施策と組み合わせることで、SEOから獲得したリードを確実に商談・成約につなげやすくなります。
BtoBのSEOで陥りがちな失敗例には「キーワード選定が曖昧」「コンテンツが専門的すぎてユーザー視点が抜け落ちる」「社内リソース不足で施策が放置される」「外部委託だけで終わり、社内ノウハウが蓄積しない」などがあります。
これらを防ぐためには、目的とKPIを明確化したうえで小さく始め、定期的に分析・改善を繰り返しながら運用体制を整えていくことが欠かせません。継続的に成果を生むためには、SEOをマーケティング全体の戦略と連動させることがポイントです。

実際にSEOを始める際、最初に確認すべき項目や運用開始後に定期的にチェックすべきポイントを整理しておくと、施策の抜け漏れや方向性のブレを防ぐことができます。
BtoB企業がSEOを始める前に押さえておきたい事前確認事項です。
運用フェーズでは定期的に下記項目を確認し、改善を続けることが大切です。
これらを定期的にモニタリングしながら、SEO施策を常に最適化していくことが、BtoBでの成功の鍵となります。
BtoB企業にとって、SEO対策はリード獲得やブランド力向上、競合優位性の確立など、マーケティング戦略の中核を担う重要な施策です。
特に、購買担当者が検討段階で行うWeb検索において、自社の専門性や独自の強みを発信し続けることで、長期的なビジネス成長を支える集客基盤を構築できます。
今回紹介した成功事例やステップ、注意点、チェックリストなどを参考に、まずは小さく始め、継続的な分析・改善を繰り返しながら運用体制を整えていくことが大切です。
広告や展示会、SNSなど他施策との併用もうまく活用しつつ、SEOをBtoBビジネスの成長エンジンとしてぜひ取り入れてみてください。
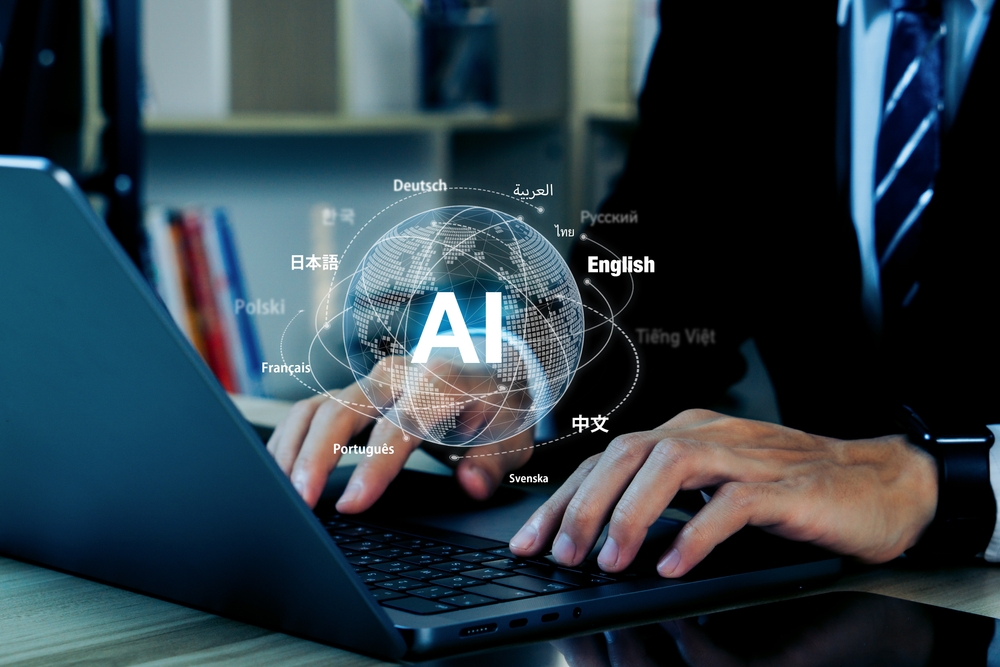
SEO対策をしたいけど「方法がわからない」「リソースが足りない」という際はProteaにご相談ください。
サイトの状況を確認し、各社の課題にあった提案をさせていただきます。
お問合せはこちら
また、AI記事サービスの「AIフォースSEO」も提供しております。
AIフォースSEOは1記事5,000円から作成可能な記事生成サービスです。
キーワード選定がプラスされたプランもご用意しております。
SEO対策を実施したいけど、自社にノウハウがない、リソースが足りないなどでお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
AIフォースSEOのお問合せはこちら
この記事を書いた専門家(アドバイザー)
著者情報 プロテア
WEBマーケティングの領域で様々な手法を使い、お客さまの課題を解決する会社です。