SEOに力を入れているのに順位が伸びない、アクセスが頭打ちだと感じることはありませんか。原因のひとつに、同じ検索意図を狙う複数ページが評価を奪い合うSEOにおけるキーワードカニバリゼーション(カニバリ)があります。
この記事では、カニバリが検索順位やクリック率に与える悪影響、見つけ方と便利なツール、短時間で着手できる解消手順までを実践的に解説します。
SEOにおけるカニバリが気になっている人は、ぜひ参考にしてください。
目次

SEOにおける「カニバリゼーション(キーワードカニバリ)」とは、同じ検索意図や近いキーワードを狙う複数ページが互いに競合し、評価や順位、クリックが分散してしまう現象を指します。
サイトの規模が大きくなるほどテーマの重複が起きやすく、リライトや新規追加を繰り返す運用ではさらに発生率が上がります。結果として、狙ったページとは別のページが上位に出る、検索順位が日ごとに入れ替わる、クリック率が低いページにトラフィックが流れるといった問題が起こります。
これらはサイト全体の集客効率やコンバージョンに悪影響を与えるため、早期発見と計画的な解消が必要です。たとえば「SEO対策」という語で、基礎解説、事例、サービス案内の3ページを個別に作成すると、それぞれが同じ意図で競合しやすく、どのページも本来の力を出せません。
定義や仕組みを理解し、原因と影響を把握したうえで、正しいチェックと対処を行うことが重要です。
カニバリゼーションは、サイト内の複数ページが同一または近似の検索意図をカバーし、検索エンジンがどのページを優先表示すべきか判断しづらくなる状態を言います。
理想は「1ページ1検索意図」ですが、トピックを深掘りする過程や更新の積み重ねで境界が曖昧になりやすいです。
このとき評価シグナルが分かれ、1つのキーワードで2ページが10位〜20位に並ぶ、あるいは日替わりで別ページが浮上と沈下を繰り返すなどの症状が現れます。
重複コンテンツのような明確なペナルティではありませんが、被リンク、内部リンク、クリック、滞在などの指標が散らばるため、本来届くはずの順位や流入を逃す要因になります。
予防設計、定期的な検査、素早い修正の3点を運用の基本に据えることが有効です。
キーワードカニバリは、運用体制や情報設計、更新手順の小さなほころびから生まれます。代表的な要素は次の3つです。
企画段階で意図の領域を整理し、公開後も重複を監視すれば発生率を大きく下げられます。以下でそれぞれの特徴と注意点を解説します。
長期運用では異なる執筆者や時期に作られた記事が、気づかないうちに同じ検索意図を狙ってしまうことがあります。
例えば「SEO対策」で基礎解説、成功事例、ツール紹介を個別に用意すると、Googleはどのページを該当クエリの代表として提示すべきか迷います。
結果としてある日はA記事、別の日はB記事が上がるなど順位が不安定になり、双方が本来の流入やコンバージョンを取り逃します。
テーマの深掘り自体は有益ですが、検索意図の粒度をページごとに明確化し、公開前に既存記事との役割が重なっていないかを必ず確認してください。
トピッククラスターを採用する場合も、親子関係と内部リンクの方向性を定義して、代表ページを明示することが望ましいです。
カテゴリやタグ、アーカイブなどの情報設計が曖昧だと、意図の近いURLが並立し、同じキーワード軸で競合しやすくなります。
といった状況は、検索エンジンにもユーザーにも判断の迷いを生みます。
さらに、ピラーページとサブページの役割が重複すると、重要度のシグナルがぼけてクロール効率も落ちます。
想定読者の導線を基準に階層を整理し、各層のページに固有の検索意図を割り当ててください。ナビゲーション、パンくず、サイトマップを一貫させ、代表ページへ内部リンクを集中させると、カニバリゼーションを抑制できます。
情報更新を重ねると、過去記事と内容やキーワードの重複が生まれがちです。
古い記事をリフレッシュしたのに、同テーマの新規記事を同時に公開すると、両方が同じ検索意図を取りに行きます。
さらに、年版や比較表などの量産で似通ったページが増えると、評価とクリックが分散します。更新前には対象クエリの代表ページを特定し、強化はそのページに集約する方針を取ってください。
役割が重なるページは統合し、旧URLは適切なリダイレクトで評価を移行します。意図の棲み分けが難しい場合は、noindexや内部リンクの再設計を選択肢に入れ、ユーザー体験と検索意図の整合が取れる形に調整することが有効です。
カニバリを放置すると、順位の不安定化、クリックと被リンクの分散、意図しないページの上位表示、クロールバジェットの浪費、ユーザーの迷いと離脱の増加など、複数のマイナスが重なります。
評価するポイントが割れるため、競合より質が高いページでも上位に届きにくく、広告や他チャネルの効率まで悪くなることがあります。
運用面では計測が難しくなり、改善の当たりを付けにくくなる点も問題です。
早期の検出と是正により、代表ページへ評価と内部リンクを集めるだけで、順位とクリックの伸びが見込めるケースは多いです。次に起こりやすい症状と仕組みを解きほぐします。
同一意図に複数ページが並ぶと、検索エンジンはどれを最適解として提示すべきか判断しづらくなります。
特定のクエリに対し、日や状況によって異なるページが評価されやすくなり、昨日は1位でも今日は圏外、あるいは10位前後を行き来するといった変動が起きます。
これにより集客計画が立てにくく、検証期間中のデータもぶれやすくなります。さらに、コンバージョン率が低い記事が偶然上位に出続けると、流入はあっても成果につながりにくくなります。
変動が激しい、意図と違うページが上がるといった兆候が見えたら、対象クエリの代表ページを定め、内部リンクとコンテンツの役割を整理して優先度を明確化することが重要です。
カニバリでは、本来1ページに集まるはずの被リンク、内部リンク、クリック、滞在や回遊などのシグナルが複数ページへ分かれます。
評価が細切れになると、いずれのページも決定力に欠け、結果的に競合に上位を譲りやすくなります。特にアンカーテキストがばらける内部リンク構造は、どのページが代表かを曖昧にし、検索エンジンの理解を難しくします。
解消の基本は集約です。役割が重複するページは統合し、旧URLから代表URLへリダイレクトで評価を移し、関連ページからの内部リンクを一本化します。
これにより評価シグナルがまとまり、狙ったクエリでの可視性が高まりやすくなります。
あわせてタイトル、見出し、導入の意図を統一し、検索意図との適合を高めてください。
SEO対策を継続するうえで、キーワードカニバリの有無を定期的に確認することは非常に重要です。カニバリは自然に解消しにくく、見落とすと評価やクリックが分散し、狙ったページの可視性が落ちます。
日々の順位変動と検索結果に出るURLの観察、Google検索演算子やGoogle Search Consoleを使った手動検証、さらにAhrefsやSE Ranking、Ubersuggestなどの専用ツールを併用し、兆候を早期に把握してください。
異常が見つかったら原因と対象URLを特定し、優先ページへ評価を集める施策へ素早くつなげることが、SEOパフォーマンス維持と改善の近道です。
発生時に表れやすい変化を早期に捉えると、不要な施策を避けつつ的確に対処できます。次の現象が同時に観測されるほど、カニバリの可能性は高まります。気づいた段階で対象クエリと表示URLを優先的に深掘りし、代表ページの整理に着手してください。
これらは日次モニタリングの着眼点として常に確認すると効果的です。
あるキーワードの検索結果で日や週ごとに異なる自社ページが入れ替わり上位表示される場合、評価が分散している可能性が高いです。例えば「カニバリ SEO」で月曜はA記事、火曜はB記事が上位、水曜はどちらも沈むといった動きは典型的です。
Googleが代表として提示すべきURLを決めかねる状態では、クリックや被リンクの蓄積も分かれ、安定した成果を得にくくなります。
まず、表示URLの推移を時系列で確認し、意図する代表ページが常に出ているか、突然別URLへ切り替わっていないかを見極めてください。異常が続く場合は、内部リンクやタイトル、見出しの役割を整理し、評価を集約する対策が有効です。
同じ検索キーワードに対して自社の複数URLが同時に並ぶ状況は、一見有利に見えても評価が二分されるため望ましくありません。
1ページに評価と被リンクが集まっていればより高い順位を狙えた可能性があり、ユーザー側でもどちらを選ぶか迷いが生じます。検索意図が重なるページが並立しているサインでもあるため、代表ページの定義と役割のすみ分けを優先してください。
該当クエリで表示される各URLの目的、想定読者、コンバージョン導線を比較し、重複する要素は統合や内部リンクの再設計で一本化します。必要に応じて旧URLは適切にリダイレクトし、評価を集中させることが効果的です。
専用ツールがなくても、毎日の運用で使える手動の確認方法があります。基本はGoogle検索の演算子による事前調査と、Google Search Consoleでの表示URLと順位推移の検証です。公開前の重複防止と、公開後の早期検出の両面でうまく使い分けると良いでしょう。
site:演算子(例:site:protea-inc.co.jp)で既存ページの重なりを洗い出し、Search Consoleではクエリ単位で複数URLが並んでいないか、期間比較でURLが入れ替わっていないかを点検します。簡便かつ再現性が高く、定期モニタリングに向く方法です。
検索窓に「site:自社ドメイン キーワード」と入力すると、指定キーワードを含む自社ページの候補を一覧できます。
例えば「site:example.com カニバリ SEO」で関連ページの並びを確認し、想定外のURLや似た内容のページがないかを見ます。
さらに「intitle:キーワード」「inurl:スラッグ」「”完全一致の語句”」「-除外語」などの演算子を組み合わせると、重複の疑いを絞り込めます。
公開前の企画段階でも同様の手順で既存コンテンツと役割が被らないかを確認してください。
site:の結果は参考指標にとどまるため、実際の検索結果とSearch Consoleのデータで裏取りを行い、表示URLと順位の実態を合わせて評価することが重要です。
Search Consoleの「検索パフォーマンス」で気になるクエリを指定し、「ページ」タブで実際に表示されたURLを確認してください。
確認した際に、1つのクエリに対して複数URLが並ぶ、または期間比較で表示URLが頻繁に入れ替わる場合はカニバリの可能性が高いです。
併せて「日付」範囲を切り替え、施策前後の順位とCTRの推移を点検してください。
意図する代表URLの掲載率が低い、CTRが高いのに別URLが表示され続けるといった兆候は要注意です。
ページ側のレポートでは対象URLの掲載クエリ一覧を見て、役割が重なる近接クエリがないかも確認します。
検出後は内部リンクの見直し、タイトルと見出しの再定義、不要URLの統合やnoindexなどの対処を段階的に実行します。
手動確認に加えて、専用ツールを併用すると検出の精度とスピードが大きく向上します。特に中規模以上のサイトや多くのキーワードを運用する場合、定点観測とアラート機能が役立ちます。代表的な選択肢は次のとおりです。
いずれも表示URLと順位の推移を把握でき、複数URLの同時ランクインや入れ替わりを素早く検知できます。予算や体制に合わせて組み合わせてください。
Ahrefsでは「Organic keywords」や「Site Explorer」でキーワードごとのランクインURLを一覧できます。1つのキーワードに対して複数URLが紐づいていれば、カニバリの疑いを即座に把握できます。
履歴表示を使えば、同一クエリで表示URLが切り替わるタイミングも追跡可能です。CSVエクスポート後にスプレッドシートで「キーワードでグループ化→URL件数が2以上」を抽出すると、問題箇所を効率的に洗い出せます。
検出後は代表URLを決め、アンカーテキストを統一し、重複ページは統合やリダイレクトで評価を集めます。
変更点は注釈を残し、翌週以降の順位とCTRの改善を継続監視する運用が有効です。
SE Rankingはキーワードごとの順位と表示URLの変化を日次で記録し、入れ替わりを可視化できます。
特定キーワードでURLが頻繁に変わる、意図しないURLが上位に固定されるといった挙動を検出したら、アラートで即時に把握できます。
レポートでは期間比較が容易なため、統合や内部リンク再設計の前後で順位とCTR、可視性の推移を評価しやすい点も利点です。タグ機能で対象クエリ群を束ね、注釈で対処日を記録すると、PDCAの再現性が高まります。
中〜大規模のサイトで多数のクエリを追う場合に、手動確認の抜け漏れを防ぐ補助線として活用してください。
Ubersuggestなどの無料ツールでも、基本的な順位推移や表示URLの確認、競合状況の概観が可能です。小規模サイトや予算制約がある場合は、Search Consoleと組み合わせて初期の検出と経過観察に活用できます。
ただし無料版はデータの粒度や履歴期間に制限があるため、URL入れ替わりの細かな追跡や大量のキーワード管理には向きません。
週次の手動チェックとあわせて、代表URLの定義、内部リンクの整備、統合やリダイレクトの実施状況を一覧化し、必要に応じて有料ツールへ段階的に移行する判断をおすすめします。
目的と規模に応じたツール選択が、無駄のない運用につながります。
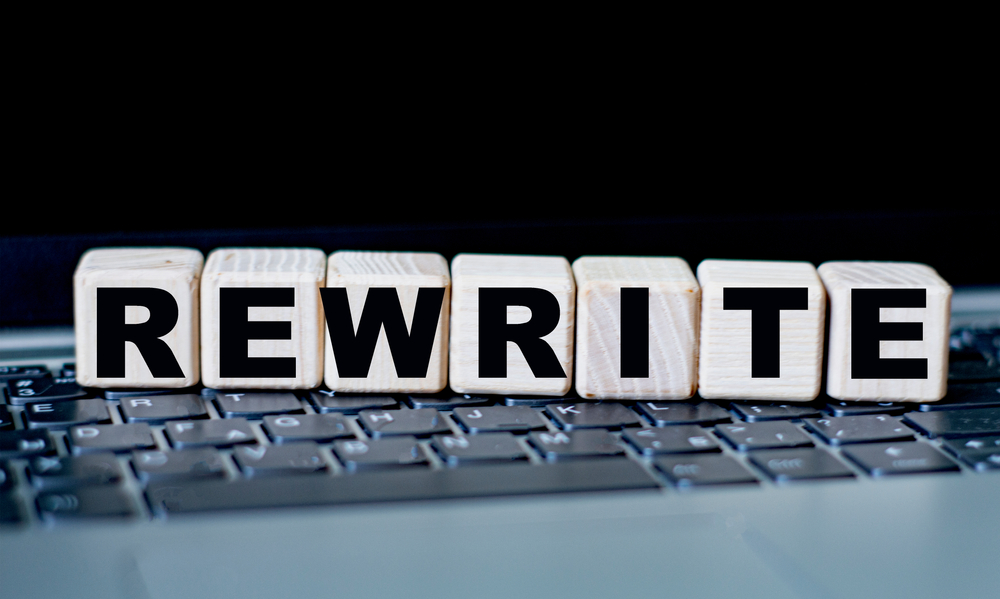
キーワードカニバリは検索評価やトラフィックの分散を招き、想定したページが上位に定着しない原因になります。
放置するとクリック率やCVの損失だけでなく、計測の難易度も上がり改善判断が遅れます。効果的に解消するには、現状の把握、代表ページの決定、役割のすみ分け、集約の実装という順序で進めることが重要です。
本節では、調査から実装、再発防止までを段階的に整理し、リライト、統合、内部リンク最適化を中心とした実務的な手順を具体的に解説します。
自社のリソースやサイト規模に合わせて優先度を決め、評価の集中と順位の安定化を実現してください。
最初に対象範囲と目的を明確化し、代表ページを定義します。次に対象URLとクエリを洗い出し、影響度で優先順位を付けます。最後に「強化するページ」と「役割を譲るページ」を決め、集約プランへ落とし込みます。
定量データと意図の整合を併せて評価する姿勢が大切です。
検出はSearch Consoleの「検索パフォーマンス」でクエリを指定し、「ページ」タブで同一クエリに複数URLが並ぶ事象を確認するところから始めます。先述したsite:演算子やintitle:、inurl:も併用し、想定外の候補URLを漏れなく抽出します。
AhrefsやSemrushで「Organic keywords」をエクスポートし、スプレッドシートで「キーワードごとにURL数」を集計すると、重複の全体像を短時間で俯瞰できます。
併せて各URLの順位、CTR、セッション、CV、被リンク、本数などを記録し、インパクトの大きい箇所から着手できるように指標を整えます。
洗い出し段階で代表候補となるURLの強みと弱みをメモしておくと、後続の統合やリライトが効率化します。
各ページの検索意図を「情報収集」「比較検討」「購入・問い合わせ」などの段階で再分類し、1ページ1検索意図を徹底します。
キーワードプランナーや関連語ツールで近接語を棚卸しし、意図が衝突する語を代表ページに寄せ、別意図の語は支援ページに割り当てます。
タイトル、H1、H2、導入、本文の主題が割り当てた意図と一致しているかを点検し、曖昧な言い回しや重複する見出しを整理します。検索タブのSERPを実際に確認し、上位ページの意図とフォーマット(ガイド、比較、事例、FAQなど)に対して自ページの役割が明確かを検証してください。
意図の再定義を終えたら、追跡クエリと代表URLの対応表を作成し、運用チームで共有します。
リライトの目的は、ページ同士の役割を分け、検索エンジンとユーザーに違いを明瞭に伝えることです。
単なる表現の置き換えではなく、構成、見出し、内部リンク、タイトル、メタ情報まで一貫性を持って最適化します。代表ページは包括的に、支援ページは特定テーマに深く寄せる方針が有効です。
競合するページの見出し構成と本文を横並び比較し、重複している節や似通った主張を特定します。
代表ページでは検索意図全体を満たす体系的な構成に改め、支援ページではサブトピックやユースケース、ベストプラクティス、失敗例、手順などに特化させます。
重複パラグラフは片方に集約し、もう一方は補足的な角度に書き換えます。独自データ、図表、事例、内部リンクでの深掘り先を明示することで、ページ間の役割が自然に分割されます。
導入と結論で対象読者と解決できる課題を明言し、意図のズレをなくすと、評価とクリックの集中を後押しできます。
タイトルとH1は代表クエリを正面から掲示し、支援ページはロングテールや近接語に振り分けます。
本文では主要クエリの乱用を避け、各ページの主題語と補助語の関係を明確にします。メタディスクリプションは意図に即したベネフィットと行動を提示し、誤クリックを減らします。
内部リンクのアンカーは代表クエリに統一し、支援ページから代表ページへ評価が流れる設計にします。
変更後はSearch Consoleでクエリ別の表示URLが安定したか、CTRが改善したかを期間比較で確認し、必要に応じて見出しや導入の表現を微調整してください。
役割や内容が大きく重なる場合は、統合で評価を一箇所に集める決断が有効です。統合先の設計、内容の集約、301の実装、内部リンクの修正、構造化データやサイトマップの更新までを一連の作業として計画します。統合前後の指標を記録し、変化を追える状態にしておくと検証が容易です。
統合先は検索意図に対して最適な見出し体系を組み、統合元の有益な段落や図表、FAQを取捨選択して再配置します。重複は1つにまとめ、情報の鮮度と正確性を担保します。
パンくずや関連記事、目次を整え、回遊先として支援ページを適切に配置します。構造化データや画像の代替テキストも更新し、旧URLに存在した内部リンクの価値を損なわないように移設します。
公開後はクロールとインデックスの状況、クリックとCTR、スクロール深度などを追い、必要な追加情報を素早く補強します。
統合元から統合先へ301を設定し、チェーンやループが発生しないよう一対一で実装します。正規化(canonical)やhreflang、構造化データの参照先を統合先に合わせ、XMLサイトマップから旧URLを除外します。
内部リンクは全て新URLへ更新し、外部リンクの重要な参照元には可能な範囲で更新依頼を送ります。Search Consoleで「ページが削除されました」などの検知を確認し、インデックスの切替と順位の推移を観察します。
必要に応じて統合先の内容を増補し、検索意図との一致度を高めて定着を図ります。
内部リンクは評価と需要を代表ページへ導く強力なレバーです。アンカーの統一、階層と回遊導線の整理、重複を生むリンクの削除によって、検索エンジンに重要度の中心を明確に伝えられます。UXの改善とも両立しやすいため、定期的な棚卸しと更新を運用に組み込みましょう。
支援ページ、関連コラム、カテゴリ、タグ、ランキングなどから代表ページへ計画的に内部リンクを集めます。アンカーには代表クエリや近接語を自然に含め、同義の表現を乱立させず方向性を統一します。グローバルナビ、パンくず、サイドバー、フッターの導線も見直し、重要ページへの距離を短縮します。
更新記事には必ず代表ページへのリンクを追加し、クロール頻度と認知を高めます。リンク追加後は代表ページの表示回数、CTR、掲載順位の推移を追い、過剰なリンクや不自然なアンカーがないかを点検してください。
代表ページと競合するURLへのリンクや、カニバリキーワードを含む過剰なアンカーは整理します。関連記事自動出力で意図の重なるページが露出していないか、ウィジェットやテンプレートで不要リンクが量産されていないかを確認します。
noindexにしたページやアーカイブへのリンクは役割に応じて抑制し、サイトマップとナビゲーションに一貫性を持たせます。
削除後はクローラビリティと回遊の指標を確認し、代表ページへの集中度が高まったかを評価します。必要に応じてアンカーの語彙を整理し、過不足のない内部導線に更新してください。

SEOカニバリは発生後の修正に時間と労力がかかるため、最初から防げる仕組みづくりが重要です。設計段階ではページの役割と検索意図のすみ分けを明確化し、運用段階では重複の芽を早期に検出できるルールと監視体制を整備します。
キーワードマッピング、カテゴリとURLの統一方針、テンプレート化された原稿フロー、公開前審査、定期モニタリングまでを一連のプロセスとして定義し、関係者全員で同じ基準を運用すると、長期的な順位安定と工数削減につながります。
カニバリを防ぐ土台は情報設計の精度です。
検索意図に基づく階層構造を定義し、カテゴリ、ピラーページ、サポート記事の役割を決めます。URLとパンくずを整え、内部リンクの方向性を統一すると、代表ページが明確になり重複が起きにくくなります。
設計書と運用ルールを文書化し、追加開発や記事増加時にも判断を迷わない体制を作ることが大切です。
キーワードマッピングは各ページの検索意図、主要クエリ、補助クエリ、想定読者、コンバージョンを一枚に整理する手法です。新規記事やリライトのたびに参照できる単一の表を運用すれば、同一意図の重複や近接語の衝突を事前に防げます。
作成時はクエリを意図別に分類し、代表ページを必ず一つに決め、支援ページとの関係を明示します。併せてアンカーテキストの指針、スラッグの命名規則、正規化やインデックス方針の列を設けると、制作から公開までの判断が揃います。
変更履歴を残し、四半期ごとに見直すことで、拡張時の不整合も抑えられます。
カテゴリはサイトの主題とユーザーの探索行動に沿って設計します。抽象度をそろえ、階層ごとに扱う検索意図の範囲を定義し、カテゴリページは包括的ガイド、子ページは特定テーマの深掘りと位置づけます。
重複を避けるため、カテゴリ間で同じ意図を扱わないルールを設け、タグは補助的な軸に限定します。URLは短く一貫性を保ち、パンくずと内部リンクで代表ページへ評価が集まる導線を整えます。
カテゴリのトップには要点を整理した導入とハブ的なリンク群を配置し、子ページへ明確に分岐させると、検索エンジンとユーザーの双方に構造が伝わりやすくなります。
制作フローにカニバリ防止の関門を組み込むと、公開後の手戻りが減ります。
企画段階で既存資産との競合を確認し、下書き段階で見出しと意図の重複を点検、公開直前にチェックリストで最終確認します。
原稿テンプレートには想定クエリ、読者、意図、内部リンク先、除外すべきクエリの欄を用意し、編集とSEO担当が共同で承認する体制を整えることが有効です。
企画時はターゲットクエリの検索結果を確認し、上位ページの意図、フォーマット、情報の深さを観察します。自社の既存記事とクエリ対応表を突き合わせ、同一意図やスラッグの競合がないかを確認してください。
重複の可能性がある場合は既存記事を強化する選択を優先し、新規で作る場合は意図の粒度をずらすか、別フェーズの読者に役割を分けます。
計画書には代表ページと支援ページの関係、内部リンクの向き、アンカーの表記統一を明記し、公開後の評価集約まで見据えた企画に仕上げます。
公開直前はタイトル、H1、見出し、導入、メタ、URL、内部リンクを対象に重複を点検します。代表クエリがどのページでも重なっていないか、アンカーがばらついていないか、支援ページが代表ページへ正しく案内しているかを確認してください。
必要に応じてcanonicalやnoindexを設定し、関連記事ウィジェットの出力で競合URLが並ばないよう調整します。最終チェックは二名以上で担当し、チェックリストと注釈を残すことで後日の検証が容易になります。
運用フェーズでは早期検知と迅速な修正が成果を左右します。Search Consoleでクエリ別の表示URLを確認し、入れ替わりや複数URL同時表示を監視します。
順位追跡ツールのアラートや週次レポートを活用し、異常が出たクエリを優先的に確認します。
検出から対処までの手順を標準化し、対応履歴を記録すると再発防止になります。
検索パフォーマンスで対象クエリを絞り、「ページ」タブで表示URLの数と入れ替わりを確認します。
期間比較で代表URLの掲載率、CTR、平均掲載順位を追い、意図と異なるURLが上がっていないかを点検してください。
問題が見つかったら、タイトルと見出しの再定義、内部リンクの整理、不要URLの統合や正規化を順に実施します。注釈とダッシュボードを用意し、対策日と結果を紐づけると改善の因果関係が把握しやすくなります。
月次で傾向を振り返り、マッピング表とテンプレートに月間状況を記録しましょう。
順位追跡とURL監視を自動化すると、規模が大きいサイトでも抜け漏れを抑えられます。
キーワードごとの表示URLが切り替わったときに通知するルール、複数URL同時ランクインのフラグ、重要クエリの大幅な順位変動のアラートを設定してください。
定例会議ではダッシュボードを共有し、代表URLの安定度、CTRの推移、統合後の改善を確認します。検出時の対応テンプレートを整えておけば、リライト、統合、内部リンク修正まで一気通貫で進められ、評価の集中と再発抑止が実現します。
SEOにおけるカニバリゼーションは、検索順位やサイト流入の低下、ユーザー混乱など多くの悪影響を及ぼすため、早期発見・早期対策が不可欠です。カニバリ解消のためには、該当ページの洗い出し・キーワードの明確化・リライトやページ統合・内部リンク最適化といったSEO施策を段階的かつ体系的に実施しましょう。
また、未然防止のためのサイト構造設計や運用体制の整備、定期的なモニタリングとツールの活用も重要です。SEO視点でのカニバリ対策を徹底し、サイト全体の評価と検索順位の安定化、ユーザー体験の向上を同時に実現することで、長期的なSEO成果の最大化が期待できます。
「記事を投稿してるけど中々順位が上がらない」「自社のリソースが足りなくてSEO対策ができていない」などのお悩みがありましたらProtea にお任せください。
Proteaは生成AIを組み込んだ記事代行サービス「AIフォースSEO」を展開し、従来の約5分の1の納期でSEOに強い高品質コンテンツを提供しています。
加えて、AI Overviewの影響に関する分析記事やE-E-A-Tの強化ノウハウを自社メディアで公開するなど、最新トレンドを実務に落とし込むスピードが強みです。
実際に自社で公開している記事でもSEOでの上位表示、AIOへの表示が複数あります。
ただいま、【1記事無料お試しキャンペーン】を実施しておりますので、気になった方は是非まずは1記事を無料でお試しください!!
※お試し記事は料金は発生いたしません。お試し記事後の契約は任意となります。追加料金が発生することもございません。
この記事を書いた専門家(アドバイザー)
著者情報 プロテア
WEBマーケティングの領域で様々な手法を使い、お客さまの課題を解決する会社です。